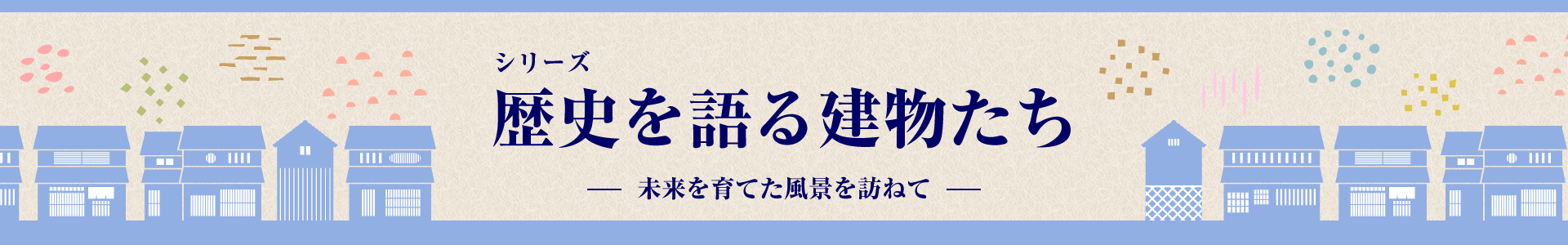

- この記事の企画
- 文化財指定を受けた有名建造物から、街中にひっそりとたたずむ建物まで幅広くスポットを当て、それらの歴史的経緯やエピソードなどをお届けします。
山形県南陽市の赤湯駅から西置賜郡白鷹町の荒砥駅につながるフラワー長井線は、第三セクターの鉄道会社である山形鉄道株式会社が運営する全長30.5kmの路線である。17の駅舎のうち、西大塚駅(川西町、大正3年開設)と羽前成田駅(長井市、大正11年開設)は、ほぼ当時のまま残る木造駅舎で、いずれも平成27年に国の登録有形文化財に指定されている。本稿では、地域住民が駅の維持管理に積極的に関わっている羽前成田駅を取り上げる。

マーケティングに基づいて作られた駅
『長井市史 第三巻・近現代史』によると、明治33年、奥羽本線の米沢-赤湯間が開通し、赤湯が東京と鉄道で結ばれることになった。それから12年後の明治45年、西置賜郡軽便鉄道期成同盟会が設立された。当時、政府では赤湯-長井の軽便鉄道敷設を予定していたが、同盟会の要望は、それをさらに延伸して、荒砥までの敷設を求めるものであった。
政府は予定通り、大正3年までに赤湯-長井間の鉄道を敷設したが、期成同盟会の陳情は続いた。そのかいあって、大正11年には長井-鮎貝間が開通し、翌12年には鮎貝-荒砥間が完成した。これで、赤湯を起点とし、荒砥を終点とする長井線30.5kmは全線開通となった。長井-鮎貝の間にある羽前成田駅は、その時に建設されたものである。まさしく先人の熱意が実を結んだものである。

画像提供:羽前成田駅前おらだの会
ところで、駅をどこに作るかについては、時として地域間の猛烈な誘致合戦が起こることがある。しかし、羽前成田駅に関しては、そのような誘致合戦の記録はない。羽前成田駅の設置にあたっては、どのくらいの乗客が見込まれ、どのくらいの収益が見込まれるかが計算され、国会でも報告がなされている。今でいうところのマーケティングが、駅の設置場所にあたっては綿密に行われていたといえる。
国鉄からJR、そして第三セクターへ
長井線は、戦後の日本国有鉄道法の発足で国鉄長井線となったが、長らく赤字路線であった。昭和63年4月1日、国鉄が分割民営化され、新たにJRグループが発足した。同じく昭和63年4月20日、第三セクター方式による山形鉄道株式会社の創立総会が開催され、10月25日、山形鉄道株式会社がJR長井線を引き継ぐ形で営業を開始した(山形鉄道ウェブサイトより)。
この流れを見ると、赤字路線の廃線は、国鉄の分割民営化によって行われたと認識されがちだが、両者は全く別の政策である。
昭和55年に制定された国鉄再建法では、全国83路線のいわゆる「赤字ローカル線」を、バスへの転換などによって順次廃線とすることを決めた。第1次対象(昭和56年、40路線)、第2次対象(昭和59~60年、31路線)、第3次対象(昭和61~62年、12路線)、のうち、長井線は第3次対象に指定された。
廃線に伴いバス路線に転換するケースが少なくない中、長井線は第三セクター(フラワー長井線)として出発する道を選んだ。この決断がなかったら、羽前成田駅は残ることはなかったかもしれない。
現在は、羽前成田駅前おらだの会が管理
昭和63年に山形鉄道株式会社がフラワー長井線を運営してから、新駅ができたり、それまでの木造駅舎が建て替えらえられたりするケースが相次いでいる。しかし、山形鉄道株式会社の中井晃社長によると、駅舎の新設や建て替えは、会社ではなく地元自治体が行っているという。その際、駅舎の建設だけでは議会の承認が得られないことから、公民館などを併設して「コミュニティセンター」として駅の複合機能を図るケースが多いという。
それでは、なぜ羽前成田駅は木造のまま残っているのか。羽前成田駅前おらだの会の齋藤理喜夫会長は、「長井市に予算がなかったこと、成田駅近くにすでに公民館や集会施設があったことから、建て替える必然性がなかったはず」と話す。なお、羽前成田駅前おらだの会は、昭和59年に結成された羽前成田駅協力会(簡易業務委託化に対応)から発展する形で、平成8年に発足した。羽前成田駅は、現在は無人駅なので、改札業務などは行わず、会の主な活動内容は、駅舎とその周辺の環境整備と、駅舎を活用したイベントなどである。
意外にも、これについて、山形鉄道とおらだの会では正式な契約書を交わしていないようだ。いわば、互いの信頼関係によって成り立っているといえる。先述の西大塚駅には、このような地域組織はない。
人生の出発点としての「駅」
築年数が長い木造駅舎である以上、劣化は避けられない。そこで、おらだの会では、長井市の住民主導のまちづくりに対する支援基金(まちづくり基金)を得て、平成23年~24年にかけて、大規模なリノベーションを行った。具体的には、サッシに改変されていた窓枠を木枠に戻すなど、建設当時の姿に戻す工事である。見えない痛みも直し、「どこを直したのかわからない」ほど上手に修繕したのが自慢である(おらだの会ブログより)。
“絵になる”木造駅舎はロケにも使われ、近年では、テレビ朝日ドラマ『十津川警部シリーズ70』(平成31年3月放送)で、ラストで犯人が逮捕されるシーンが撮影された。また、中国の大ヒットドラマ『十年三月三十日』(令和2年8月日本放送)では、雪の中、男性がプロポーズする重要なシーンが撮影された。
おらだの会の会長の齋藤さんは、「ローカル線は、故郷の季節と同様に正確に時を刻み、山や川、風と同じように地域の風景の一つとなって、私たちの中に存在してきた。駅舎は出会いや別れの場所。いろんな人生が交差する場所であって、若い世代ともイメージを共有することができる空間です」と話す。「鉄道と共に、地域の存続すら危惧される中で生きる私たちがいる。無縁社会といわれる時代に生きて、旅の途中でひなびた駅舎に降り立つ人がいる。駅舎が今もなおそのまま残っていることの意味を、共に考えていく必要があるのだろう」と問いかける。
ヒアリングを終えて、大変大きな宿題をいただいた気がした。

この記事を書いた人

熊本学園大学 経済学部
准教授山口 泰史
2001年、東京大学大学院単位取得退学。博士(学術)。前フィデア総合研究所(現フィデア情報総研)主任研究員。2019年より現職。専門は人口地理学だが、歴史的建造物の保存活用にも関心を持つ。前職より本シリーズの連載を続けている。




